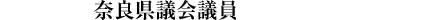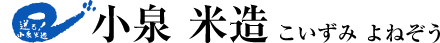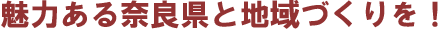議会報告ASSEMBLY REPORT
2017.12.14 カテゴリ:平成29年9月定例会 代表質問答弁
◆三十九番(小泉米造)
(登壇)議長のお許しを得ましたので、自民党奈良を代表いたしまして、私、小泉米造が県政の諸課題について質問を行います。
質問に入ります前に、最近、国民・県民の生命と安全を脅かす北朝鮮による暴挙が毎日のように報じられています。八月二十九日の我が国上空を通過するミサイル発射に続き、九月三日に六回目の核実験を行ったことを受け、十一日に国連安全保障理事会が新たな制裁決議案を全会一致で採択すると、あたかもそれに対する回答のごとく、先週金曜日の十五日に、またもや北海道上空を通過するミサイルを発射しました。このような北朝鮮の暴挙は断じて許しがたく、強く非難するものであります。国際社会の団結により、一刻も早く、この問題が解決し、国民・県民の安全・安心が取り戻されることを切に願うところであります。
一方で、明るい話題もありました。去る九月一日、いよいよ第三十二回国民文化祭・なら二〇一七及び第十七回全国障害者芸術・文化祭なら大会が開会し、翌二日には皇太子殿下、同妃殿下をお迎えし、開会式が盛大に開催されました。ご承知のように、国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭が一体的に開催されるのは全国で初めてのことであります。障害のある人とない人が一体となってイベントが盛り上がり、日本文化の始まりの地、奈良のブランド力が世界に発信されることを大いに期待しながら質問に入ります。
まず最初に、リニア中央新幹線について数点、知事にお伺いいたします。
一点目は、リニア中央新幹線のルートについてであります。
これまで、三重・奈良ルートの早期実現に向けて、リニア中央新幹線建設促進奈良県期成同盟会の活動を軸としつつ、三重県と連携して、三重県・奈良県リニア中央新幹線建設促進会議を開催し、機運を醸成してきましたが、九月十一日に大阪府が加わり、名古屋以西の沿線府県である三重県、奈良県、大阪府が一致団結し、三重・奈良・大阪リニア中央新幹線建設促進決起大会が盛大に開催されました。私も出席しましたが、与党リニア議連の川崎会長、北側会長代理、自由民主党超電導リニア鉄道に関する特別委員会の竹本委員長、国土交通省の藤井鉄道局長、関西広域連合の井戸連合長、JR東海の柘植社長といった顔ぶれがそろう中で、総勢約五百名程度の関係者の参加を得て、三府県の地元団体がスクラムを組んで、三重・奈良・大阪ルートを前提とした、一日も早い着工、全線開業及びルート・駅位置の早期確定に向けた取り組みを進めていくこととしたことは非常にエポックメーキングな出来事だと考えております。
決起大会の決議文においても、一日も早い全線開業を実現することと並んで、基本計画及び整備計画に示された三重・奈良・大阪ルートを前提としたルート及び駅位置を早期に確定することが決議されるとともに、三重・奈良・大阪リニア中央新幹線建設促進会議等による新たな取り組みをスタートさせることが盛り込まれました。そこで、今般の三重県、奈良県、大阪府による決起大会をもって、京都ルートを排除し、三重・奈良・大阪ルートで決定したと考えてよいのか、知事の所見をお伺いをいたします。
二点目は、リニア中央新幹線の駅位置についてであります。
決起大会において決議したとおり、駅位置の検討に際しては、その効果が近畿全体に及ぶ交通結節性の高い位置とするとともに、乗客の乗り換え、利便性を十分に確保することが重要です。本年五月のリニア中央新幹線建設促進奈良県期成同盟会においても、奈良市附近の駅位置はリニア効果が県南部、さらには紀伊半島全体に及ぶよう、交通結節性の高い位置とすることを決議しており、近鉄が年間約一億四千万人、JR西日本が年間約三千万人を輸送している奈良県の交通体系に鑑みれば、リニア中央新幹線の奈良市附近駅は、近鉄とJRとの結節性の高い場所に設置することが望ましいと考えます。
現在のところ、奈良市、大和郡山市、生駒市の三市が中間駅設置を要望していますが、このうち大和郡山市はJR大和路線と近鉄橿原線が交差する場所を候補地としており、県内三十五市町村長を会員とし、奈良県議会議員二十名を顧問とする、「奈良県にリニアを!」の会においても、鉄道網・道路網で各地と高い交通結節性を有し、県の人口重心にも近接した大和郡山市に設置すべきことを提言しています。
したがって、リニア中央新幹線の奈良市附近駅は大和郡山市に設置することが望ましいと考えます。ルート、駅はJR東海が決定することは承知しておりますけれども、知事の所見をお聞かせください。
三点目は、奈良市附近駅を中心とした交通体系についてであります。
昨年十一月、北陸新幹線の敦賀・大阪間のルートについて検討を行っていた与党整備新幹線建設推進プロジェクトチーム・北陸新幹線敦賀・大阪間整備検討委員会の自治体ヒアリングにおいて、知事は、北陸新幹線将来ルート構想として、北陸新幹線の延伸ルートについて、奈良市附近駅でリニア中央新幹線と接続して、関西国際空港にアクセスするルートを提案したものと承知しています。
平成二十三年五月に取りまとめられた交通政策審議会の答申においても、リニア中央新幹線の整備により、三大都市圏が約一時間で結ばれる効果を最大限活用し、今後、我が国の国際競争力を維持向上させるためには、奈良県を含む三大都市圏における中央新幹線の駅と国際拠点空港の間のアクセスの利便性を十分に確保することが極めて重要とされているところです。
こうしたことを踏まえ、継続的に行っているリニア中央新幹線の調査検討事業において、今年度は奈良市附近駅と関西国際空港を結ぶ高速鉄道路線について調査を進める予定と承知しています。空港と奈良を直接結ぶのは現在リムジンバスしかなく、外国人観光客等にとっては奈良は遠い場所となってしまっており、積極的に取り組む必要があると考えています。今後、この高速鉄道路線の実現に向けて、どのように取り組んでいくのか、知事の所見をお伺いいたします。
次に、奈良県中央卸売市場の再整備について、お伺いをいたします。
私は、今年五月に県中央卸売市場開場四十周年という節目を記念して開催されました表彰式典と市場まつりに出席いたしました。特に市場まつりは、普段一般の消費者が入場できない市場の中で、ひときわ大きな卸売場を会場に、市場が取り扱う食材や近大マグロ等の販売、模擬セリなどが行われ、会場を埋め尽くした四万数千人の県民の方々とともに、卸売市場の活気を感じた次第であります。
一方で近年、市場を取り巻く流通形態が大きく変化し、取扱量、取扱金額が減少していることを市場関係者の方々からお聞きし、あわせて市場施設の老朽化の現状を目の当たりにして、新しい県中央卸売市場に生まれ変わるための将来展望が必要なことも強く感じた次第であります。
また、昨年十一月に開催された中央卸売市場の業務運営に関して調査審議する奈良県中央卸売市場運営協議会に出席し、現在検討中である将来ビジョンの経過報告を受けたところであります。今後の再整備の方向性として、従来の卸売市場の機能を高度化することはもとより、市場の規模のコンパクト化を図り、それによって生み出された余剰地を活用したいというアイデアも伺いました。
県中央卸売市場は、全国からさまざまな食材が集まる場所であることは承知しているものの、市場まつりなどの年数回のイベント時以外、普段は県民が出入りできる場所ではありません。しかし、市場で取り扱うような新鮮な食材を安く手に入れたいという県民の興味は、四十周年記念の市場まつりに四万人余が集まったことで明らかであります。
先の十二月議会において知事が答弁されましたように、市場で生み出された余剰地を県民や観光客が訪れることのできるBtoCの場に活用することは、イベントで見られた市場の集客力を常時取り込んでいくことにつながるものであり、まちづくりにとっても大いに魅力のあるアイデアであると感じています。
卸売市場用地の有効活用は全国的にも進んできており、現在再整備を計画している他の中央卸売市場においても、開かれた卸売市場を目指して、にぎわいゾーンを設ける事例がふえてきていると聞いています。例えば、近畿地方では和歌山市中央卸売市場が用地の一部に道の駅を整備する計画であり、京都市中央卸売市場は用地の一部にホテルを誘致する計画があるようであります。また、横浜市中央卸売市場でも、南部市場の一部に商業施設を誘致する計画が現在進められています。県民や観光客が訪れることのできる開かれた市場にすることは従来の卸売BtoBにとっても相乗効果が期待でき、県中央卸売市場もそのような方向性を目指すべきであると考えます。再整備に当たっては、他市場に負けないような、奈良らしい特色のあるBtoCの場が整備されることを期待しています。
今年度は県において、再整備基本構想の検討を行うと聞いていますが、BtoBについては販売力や安全・安心の強化等を図ることが、またBtoCについては、余剰地にどのような集客施設を誘致するのかが一番の課題であると考えています。その双方について、いつまでに、どのような整備をするのかをしっかり検討していただきたいと思っています。
知事は、県民や観光客が訪れることのできる開かれた卸売市場にするために、どのような再整備の構想案を考えているのか、スケジュールをあわせてお伺いをいたします。
次に、滞在型観光の推進についてお尋ねします。
観光は交流人口を増加させ、地域経済の活性化に寄与するものであり、宿泊業、飲食産業、小売業をはじめとした幅広い産業の発展や雇用の創出に大きな役割を果たしております。知事はこれまで宿泊客を県内に呼び込み、観光消費額をふやすため、さまざまな観点から観光施策に取り組んでこられました。ムジークフェストなら、奈良大立山まつりなどのイベントの充実、記紀・万葉プロジェクトの推進、奈良の歴史的資源を活用した観光プロモーションでは、平成三十年十月に予定されている興福寺中金堂落慶を核とした奈良県観光キャンペーンを展開され、県内社寺の特別拝観等を旅行商品化し、国内外のお客様にセールスするなど誘客数を伸ばしてこられました。その結果、近年の本県への入り込み客数は平成二十三年の三千三百万人から毎年増加を続け、平成二十七年は四千万人を超えております。
しかしながら、昨年の本県の宿泊客数は二百五十二万人と、全国ワーストツーに甘んじております。宿泊客は日帰り客に比べて、県内の消費額が多く、地域経済の活性化の観点からも、その増加が大きな課題となっております。県内には、法隆寺地域の仏教建造物、古都奈良の文化財、紀伊山地の霊場と参詣道の三つの世界遺産をはじめとする文化的・歴史的資源や四季折々の変化を楽しめる景観など豊富な観光素材がありますが、ホテル及び旅館の客室数は全国最下位であり、ハイシーズンには自由に宿泊施設を選択できないなど、日帰り観光の要因となっています。
現在、県が率先して宿泊施設を誘致する取り組みを進めておられ、県営プール跡地に最高級国際ブランドホテルでありますJWマリオットホテルの誘致や吉城園周辺地区と高畑町裁判所跡地においても宿泊施設の誘致に成功されました。JWマリオットホテルの進出をきっかけに、ホテル業界では奈良県が高級・上質なホテルの投資先として注目され始めている中、本年八月末には桜井市がホテル事業者と協定を締結され、橿原市や明日香村へも宿泊施設の進出が報道されております。県内の各地でも意欲ある自治体が率先して進めてこられた宿泊施設の整備が具体化しつつあることを大変うれしく思っています。
一方で、若い女性やシニア世代、外国人旅行者の間では、古民家を改修した趣のある宿泊施設の需要が大いにございます。外国人観光客は、日本でなければ購入できない物や、体験できないことに興味がある方も多いようで、宿泊費を抑えて、食事や体験を重視される方もおられます。奈良県を訪れる外国人観光客は、平成二十三年以降増加し、昨年は百六十万人を超えました。外国人観光客の増加とともに、宿泊施設に対するニーズも多様化してきています。その多様化するニーズに対応するため、高級な宿泊施設だけでなく、ゲストハウスなどの簡易宿所や本年六月に公布され、遅くとも来年六月から施行される住宅宿泊事業法、いわゆる民泊サービスなどの気軽に泊まれる小規模な宿泊施設などの充実も必要だと考えています。
そこで知事にお伺いをいたします。
観光振興により、本県経済を活性化していくためには、宿泊客をふやす滞在型観光を推進していくことが不可欠です。そのためにも、宿泊客の選択肢をふやすことが重要であり、民泊サービスをはじめバラエティー豊かな宿泊施設の充実に向けた取り組みが必要と考えますが、知事の所見をお伺いしておきます。
次に、無電柱化の取り組みについてお伺いをいたします。
無電柱化は、世界を見渡してみると、ロンドンやパリといったヨーロッパの主要都市、アジアの香港でも既に達成されており、台北、シンガポールなどでも無電柱化が進んでおります。国内に目を向けてみると、まだまだ無電柱化が十分進んでいないのが実情ですけれども、観光地における町並みの景観やたたずまいに対する関心が高まってきており、無電柱化を進めている町もございます。
例えば、石川県金沢市では景観施策の一環として、幹線道路にとどまらず、昔からある細い街路の無電柱化も積極的に行われております。また、埼玉県川越市では地域商店街や住民の積極的な働きかけにより、無電柱化が行われ、住民も地上機器を私有地に設置するという協力もあり、歴史的な町並みの保存と商店街の活性化の両方が実現されております。歴史的町並みを整備した観光地では、観光客は満足度が高く、観光客も増加しております。
このように無電柱化は、まちの景観形成や観光振興の観点から非常に効果的な施策であり、最近では防災の観点なども注目されていますけれども、観光立県を目指す奈良県においては特に観光の観点から無電柱化を推進することが重要な課題であると考えています。
ご承知のように奈良県は、三つの世界遺産や数多くの国宝や重要文化財をはじめとした歴史文化資源に恵まれています。また、世界的にも類いまれな歴史文化的な景観が大きな魅力となる地域であります。これらの魅力に触れるため、先ほど申し上げました奈良県を訪れる観光客数は近年増加傾向にあり、中でも関西国際空港へのLCCの乗り入れが増加し、関西への利便性がよくなったことなどもあって、海外からの訪問客数が増えております。奈良観光の楽しみ方の一つとして、さまざまな観光資源をめぐって歩く周遊観光が人気です。奈良の魅力は、歴史的な空間が残されていることであり、これらの魅力に触れるにはゆっくりと歩いていただくことが有効であります。
しかし、昔から利用されている道路には道幅が狭いところも多く残されています。このため、道路上にある電柱が支障となり、歩行者や自転車がくつろいで、安心安全に散策を楽しむことができないケースも見られます。また何よりも、周囲の電柱や電線が目に入ってくることで、歴史的な景色を台なしにしている例もあるのではないでしょうか。
このように、奈良県を訪れる方々に奈良の魅力を十分堪能していただくためには、電柱・電線をなくすことで、歩きやすく、世界的な観光地としてふさわしい景観を形成していくことが重要であります。そのためには、県として観光の観点から、より一層、無電柱化を推進すべきと考えています。観光地としての魅力を高める無電柱化について、現在の取り組み状況を知事にお伺いをしておきたいと思います。
次に、がん対策についてお伺いをいたします。
がんは、昭和五十六年より我が国の死因の第一位であります。およそ三人に一人ががんで亡くなっています。本県においても、昭和五十四年より死因の第一位となっており、平成二十七年では年間四千四十九人の方が亡くなっておられます。また、およそ二人に一人ががんにかかるとされていますが、高齢化の進行により、がん対策の推進は今後ますます重要になると考えられます。
県議会におきましても、がん対策の推進について重要な役割を果たすべく、平成二十一年に議員提案により、奈良県がん対策推進条例を制定し、また平成二十四年には議員全員が参加する奈良県議会がん対策推進議員連盟を立ち上げ、十月十日の奈良県がんと向き合う日における、がん検診受診キャンペーンでの街頭啓発や、がん征圧と患者支援のイベントであるリレー・フォー・ライフ・ジャパン奈良への参加、東京で開催されるがん政策サミットで他府県の方々との意見交換など、毎年さまざまな活動を行ってまいりました。中でも、先ほど紹介したリレー・フォー・ライフ・ジャパン奈良とは、がん患者やその家族、またがんを乗り越えたサバイバーや支援者などが、二十四時間一本のたすきをつないでいくリレー・ウオークですが、ことしは十月十四日、十五日の二日間、天理駅前の広場コフフンで開催される予定です。奈良県議会がん対策推進議員連盟では昨年に引き続き、チームがん議連のフラッグを掲げ参加しますが、ぜひ多くの方に参加いただき、ともに歩くことで、がんに向かう勇気や生きる感動を共有していただきたいと思います。
さて、県においてはがん対策を総合的かつ計画的に実施するために、平成二十五年に第二期奈良県がん対策推進計画を策定し、がんにならない、がんで若い人が亡くならない、全てのがん患者とその家族の苦痛が軽減され、安心、納得のいく療養生活を送ることができる、がんと向き合い、希望を持って暮らせる地域社会をつくるの三つの目標を全体目標に、がんで死亡する割合を平成十九年と比較して二〇%減少する目標を定め、がん対策の各分野でさまざまな取り組みを進めてこられましたが、まだまだ課題も多いと認識しております。
例えば、がん医療においては県立医科大学附属病院を中心に、がん診療連携拠点病院などの整備がされ、がん医療の空白医療圏であった南和地域においても南奈良総合医療センターが開院されました。医療提供体制の整備は進みましたが、県民が安心して良質な治療を受けることができるよう、医療提供体制のさらなる充実が望まれるところであります。
また、がん患者の皆さんやその家族への支援として、がん相談支援センターなどの相談窓口や患者さん同士の交流の場の設置などが進められてきましたが、多様化するがん患者の皆さんの悩みに寄り添うためには、これまで以上にきめ細やかな支援が必要となってくるのではないでしょうか。
さらに、がん予防、がんの早期発見に関してでございますが、がんの発症リスクを少なくするには、禁煙や減塩、野菜摂取など生活習慣を改善することが大切です。加えて、早期発見のためには、がん検診が特に重要であることは言うまでもありません。県では予防の取り組みとして、喫煙や塩分の過剰摂取、運動不足など、がん発生のリスクを高める生活習慣を改善する取り組みを進めてこられました。喫煙対策では、薬局で気軽に禁煙相談ができるよう、禁煙支援協力薬局の登録制度を創設されて取り組まれています。また、受診率向上に向けては、モデル市町村で効果が実証された個別受診勧奨・未受診者再勧奨の取り組みに対する県独自の補助制度の創設など、市町村の取り組みを支援されてこられましたが、受診率五〇%の目標を達成するには、さらに取り組みを強化していく必要があるのではないでしょうか。
そこで、知事にお伺いをいたします。
県では現在、来年度からの第三期奈良県がん対策推進計画の策定作業を進められているところでありますが、策定に当たっての方向性、目標をどのように考えておられるのでしょうか。また、先ほどご紹介したがん医療、がん患者の皆さんへの支援、がん予防、がんの早期発見などの取り組みについて、どのように計画に盛り込もうとされているのでしょうか、お尋ねをしておきます。
次に、大和川流域における総合治水の推進に関する条例と水害に強い奈良県の実現についてお伺いをいたします。
先ほど田中議員の質問にもありましたが、本定例県議会に大和川流域における総合治水の取り組みを一層強化するため、大和川流域における総合治水の推進に関する条例案が上程されました。本県では、戦後最大の洪水被害となりました昭和五十七年八月の洪水被害を受け、その翌年に国、県、市町村からなる大和川流域総合治水対策協議会を立ち上げ、流域全体で水害に強いまちづくりを行う総合治水対策に取り組んでまいりましたが、この条例では、大和川流域における総合治水の取り組みを一層強化するために、従来の流す対策やためる対策のほかに、控える対策を位置づけられるなど、浸水被害の軽減に向けた県の強い意志を感じているところであります。
中でも、ためる対策について、さらなる推進が図られ、雨水を一時的にためる施設等のハード対策が進められることを期待するところでありますが、一方で、今から三十年以上前に大和川流域治水対策協議会で策定された計画においても、ためる対策として位置づけられている、ため池治水利用施設の対策率が近年伸び悩み、特に市町村が担う計画目標量については、市町村間で達成度にばらつきが見られるなど、目標達成に向けた課題も見受けられます。
そこで、この大和川流域における総合治水の推進に関する条例により、雨水を一時的にためる施設等のハード対策をどのように推進しようとされているのか、知事のお考えをお伺いしておきます。
加えて、本県は亀の瀬という難攻不落の狭窄部を持つという全国的にも特殊な事情を抱えていることなどから、ハード対策の推進だけでは昨今、全国で頻繁に発生している豪雨への備えとして、必ずしも十分で万全ではないのではないかと心配もしているところであります。平成二十七年九月の関東・東北豪雨災害における鬼怒川の堤防決壊。平成二十八年八月の北海道・東北地方における中小規模河川の堤防決壊による高齢者グループホームの被災。そして、今年七月の九州北部の豪雨災害と、近年毎年のように集中豪雨による痛ましい災害が発生しています。
また報道によりますと、先週の十二日には前線を伴った低気圧の影響で、大気の状態が不安定になり、レーダーによる解析では、奈良県の各所において一時間に百ミリメートルから百二十ミリメートルの猛烈な雨が確認され、記録的短時間大雨情報が大和高田市付近や橿原市付近など複数の地点で発表されたとのことでした。
この結果、県内の河川では桜井市黒崎の大和川で、一時氾濫危険水位を超える水位状況となり、その他の九河川十二カ所の水位観測局でも水防団待機水位などの水防警報が発令されました。この降雨による人的被害は幸いにもありませんでしたが、この降雨が原因と思われる被害として、十三の市町で百十八棟の床上・床下浸水が発生し、それ以外にも道路の冠水に伴う車両の浸水被害が生じるなど、今議場におります我々だけではなく、多くの県民が新聞に掲載された写真やニュース番組での映像等で水害の恐怖を再確認されたことと思います。
これらのように、観測史上最大の総降雨量を更新したり、時間雨量が百ミリメートルを超すような、これまで経験したことのない集中豪雨による水害が一旦発生しますと、そこにお住まいの方々の尊い命や身体を一気に危険な状況に追い込み、時には家族の目の前で大切な方の命を無慈悲に奪い取ります。
またそれだけにとどまらず、その地域において、これまで積み上げてこられた財産や地域のコミュニティーを壊滅的に破壊するなど、後々にわたって人々の心に深い傷を残すことになります。ことしの六月には水防法が一部改定され、全国的にみずからの命はみずからで守る自助の意識を高めていただくようなソフト対策が進められていると聞いております。
私といたしましても、大規模な浸水による被害を最小限に抑え、水害に強い奈良県を実現するためには、整備に時間や予算を要するハード対策だけでなく、避難行動を促す減災に向けたソフト対策の充実も必要不可欠と考えますが、県ではどのような取り組みを進めているのか、その状況について知事にお伺いをいたします。
次に、近鉄郡山駅周辺地区のまちづくりについてお伺いをいたします。
本地区におきましては、人々が集いにぎわう環境整備、公共施設の再配置、安心安全で快適に移動できる環境整備をまちづくりの検討の方向として、平成二十六年十一月に県と大和郡山市がまちづくりに関する包括協定を締結されてから、約三年がたとうといたしています。その間、昨年八月には今後のまちづくりのコンセプトや将来像、基本となる取り組みを記載した近鉄郡山駅周辺地区まちづくり基本構想を策定し、地区のまちづくりについての方針が合意され、県と大和郡山市における近鉄郡山駅周辺地区のまちづくりに関する基本協定の締結がなされました。
また、今年四月には知事からの働きかけにより、県、まちづくりの中心となる大和郡山市、鉄道事業者である近畿日本鉄道株式会社の三者で、近鉄郡山駅周辺のまちづくりに関する連携協定書が締結されました。この協定では、近鉄郡山駅移設を中心とした駅利用者の安全性・利便性向上に資する駅施設整備に関すること、近鉄郡山駅利用促進につながる交流人口拡大に関すること、近鉄郡山駅周辺の公的・民的施設の整備に関すること等の検討について、三者で連携・協力しながら取り組んでいくこととされております。駅移設を中心としたまちづくりに向けての検討がいよいよ具体的に動いていくものと大変期待をいたしております。
また今年三月より、市民の方々のご意見やアイデアを伺う場としてワークショップが開催され、毎回熱い議論が重ねられたと聞いております。ワークショップの結果につきましては、毎回ニュースレターとして市内全戸に配布され、私も毎回楽しみに拝見しておりましたが、この八月二十五日に開催された第五回のワークショップをもって、一通りの議論は終えたと伺っております。今後、このワークショップでいただいた意見やアイデアをもとに、どのような計画づくりが進むのか、大変楽しみにしております。
さて、平成二十七年の九月議会の代表質問において、近鉄郡山駅周辺地区のまちづくりについて、具体的にどのような将来像を描こうとしているのかと質問させていただいたところ、知事からは近鉄郡山駅を北側に移設した上で、バスターミナルや市役所、病院、既存商店が連なる矢田町通り、郡山城跡などへのアプローチを向上させることや、大和郡山市中心市街地を東西に結ぶ通称矢田町通りについては、道幅は現在のままにして歩行者中心とし、城下町にふさわしい町並みにするなどのアイデアが示されました。
また先日も、知事のお話を聞く機会があり、矢田町通りのあり方や駅前空間のあり方など、近鉄郡山駅周辺地区のまちづくりにかけるご自身のお考えを示され、知事のこの近鉄郡山駅周辺地区のまちづくりに対する非常に強い思いを感じたところであります。
そこで知事にお尋ねします。
近鉄郡山駅周辺のまちづくりにおける具体的なまちの将来像について、どのように考えておられるのか、現在の検討状況とあわせて、お聞かせください。
最後に、小学校外国語教育の充実についてお伺いをいたします。
グローバル化の進展や人工知能の飛躍的な進化などにより、今日の社会は加速度的に変化し、将来の予測が難しくなっています。このような中でも、伝統や文化に立脚した幅広い視野を持ち、志高く未来をつくり出していくために必要な資質、能力を子どもたち一人ひとりが確実に身につけていくことが重要となっています。
特に、外国語によるコミュニケーション能力は、これまでのように一部の業種や職種だけでなく、生涯にわたるさまざまな場面で必要とされることが想定されており、今後外国語を使ってのコミュニケーション能力の向上が課題となってきます。
小学校では平成二十三年度から五、六年生で外国語活動の授業が行われ、その充実により児童の学習意欲の向上、外国語教育に対する積極性の向上といった成果が報告されています。一方で、小学校では英語の文字を扱うことが少ないことから、中学校の学習に円滑に接続されていない、英語の音とつづりが結びつきにくいなどの課題が指摘されてきました。
そのような中、小学校中学年に新たに外国語活動を導入し、外国語を用いたコミュニケーションを図る素地を育成した上で、高学年において読むこと、書くことを加えた教科としての外国語科を新設した新しい学習指導要領が告示されました。この新学習指導要領は、小学校で平成三十二年度から全面実施されるわけですが、それに先立ち、来年度から新学習指導要領の内容を一部取り入れた移行措置が実施されます。
このように高学年での教科化及び中学年からの外国語早期開始を間近に控えて、外国語教育の充実のためには小学校教員の英語力及び英語の指導力の向上がこれまで以上に求められています。教室でのそれぞれの児童のよいところ、不得手なところなどを誰よりもよく知り、児童にとって最も身近な学級担任の先生が児童とともに楽しく学びの多い英語の授業をつくることが、小学校段階の英語教育に求められている姿の一つではないかと思っているわけでございます。
しかし、現在の小学校教員の多くが修了した教育養成課程には、当時はまだ外国語活動の内容が含まれていなかったことから、教員自身からも今後の英語指導に不安があるという声も聞かれます。本県の小学校での英語の指導体制や指導内容は十分整っているのでしょうか。今後さらに充実させていく必要があるのではないかと思っております。
そこで教育長にお伺いをいたします。
新学習指導要領における外国語教育の実施に向けて、県教育委員会として、小学校教員の英語力や指導力向上のためにどのように取り組んでいくのか、お聞かせください。
以上をもちまして、代表質問を終わります。ご清聴大変ありがとうございました。(拍手)
○議長(岩田国夫) 荒井知事。
◎知事(荒井正吾) (登壇)三十九番小泉議員のご質問にお答え申し上げます。
最初の質問は、リニア中央新幹線についてでございます。
ルートが決定したのかというご質問でございますが、リニア中央新幹線の根拠法になっております全国新幹線鉄道整備法に基づく基本計画及び整備計画では、主要な経過地として奈良市附近とされているところでございます。今般の三重・奈良・大阪リニア中央新幹線建設促進決起大会は、この位置づけを踏まえ、沿線の自治体であります三重県、奈良県、大阪府で一致団結して、三重・奈良・大阪ルートを前提とした早期開業について、一体的な取り組みを進めていくこととしたものでございます。
当日は、国会議員、国土交通省鉄道局長、JR東海社長をはじめ、多数の関係者のご参加を得て、盛大に開催することができ、三重・奈良・大阪ルートの早期実現に向けた機運の醸成と関西における協力体制の充実に意を強くしたところでございます。
JR東海は、奈良市附近駅を前提とした三重・奈良・大阪ルートに賛同しておられますので、三重県、奈良県、大阪府はそれを前提として、JR東海と連携、協力する体制が整ってまいったものでございます。
具体的なルート、駅位置につきましては当日、松井大阪府知事が記者会見でお答えになったように、最終的には建設主体であるJR東海が決定されるものでございます。今後、JR東海が駅・ルートの公表に向けた準備をできるだけ速やかに進められるよう、三重県、大阪府とスクラムを組んで、必要な連携、協力を実質的に行ってまいりたいと考えているところでございます。
駅の具体的な設置についてのご所見がございました。リニア中央新幹線の奈良市附近の駅の位置はどこにすればいいのかという論点でございますが、一般論として申し上げれば、地域振興やまちづくりの観点から、リニア中央新幹線の便益がより広い地域に広がるような交通結節性の高い場所に設置されるべきと考えております。
先ほど申し上げました全国新幹線鉄道整備法にも、高速鉄道の機能の地域への均てんが大きな目標として掲げられているところでございます。他方で、リニア中央新幹線の奈良市附近駅の位置につきましては手続きがございます。JR東海が実施する環境影響評価の手続きの過程で、超電導リニアの技術的な制約、地形・地質あるいは土地利用や文化財といった立地環境の制約によって、ルートとともにおのずから絞り込まれてくるのが名古屋、東京のルート決定の実態でございます。環境影響評価が進まないと、駅の位置の具体的な確定は難しいものでございます。
したがいまして、環境影響評価の手続きに速やかに着手していただくことによって、駅位置を早期に確定できるよう連携、協力して取り組んでいくことが重要であると考えております。ルート、駅位置の具体的な確定につきましては、今申し上げましたように、建設主体であるJR東海が決められるものでございますので、今の時点でJR東海以外の者がこの地が望ましいと言えるものではないと考えております。
奈良市附近と関西国際空港を結ぶ高速鉄道路線の建設の構想について、議員お述べのように昨年十一月の与党北陸新幹線敦賀・大阪間整備検討委員会において、将来ルート構想ということで提案をいたしました。奈良市附近駅と関西国際空港を結ぶ高速鉄道路線についての構想でございますが、それについて構想を諦めたわけではございませんが、調査を進める必要があると考えております。
関空インバウンド需要を取り込むことによって、リニア中央新幹線の価値を飛躍的に高めることができるものと考えておりまして、県として調査を進めるとともに関係者に対する働きかけを行ってまいりたいと思っております。大変壮大で、かつ課題の多い難しいプロジェクトになりますので、どのように取り組むかについては、言える段階になく、まだ頭の中にそれほど固まったものがあるわけではございません。
奈良県中央卸売市場の再整備についてのご質問がございました。
現在検討しております県中央卸売市場の将来ビジョンでは、業者同士の取り引きでございます、いわゆるBtoBが基本の卸売市場に、業者と一般消費者の取り引きとされるBtoCを加えることにより、将来にわたって生鮮食料品の流通拠点としてのみならず、県民や観光客が訪れることのできる地域のにぎわいの拠点とすることを目指したいと考えています。
議員から他市場における取り組み事例をご紹介いただきましたが、にぎわいの拠点とするためにはご指摘のとおり、BtoCとして、どのような施設にするのかが肝要であろうかと思います。先進性と奈良らしさを最大限生かした施設づくりを検討する必要があると思ってまいりました。
その一例でございますが、イタリア、アメリカ、とりわけニューヨークで事業を展開し、人気の高いイータリーの思想や店づくりに注目をしております。イータリーという言葉は食べるというeatとイタリアを合わせた造語でございますが、そのコンセプトはまさしくイタリア食材を楽しく食べる、買うだけでなく、生産者、加工業者、調理人の顔やその食材にまつわるストーリーを学ぶというものです。店舗の中でおいしく、健康によい食材、さらに調理方法までをエンターテインメント性を豊かに提供しているコンセプトの場でございます。奈良県の豊かな食材の提供の仕方として、大変魅力的な考えであろうかと思っております。
今後このようなイータリー的思想も参考にしながら、奈良県のありとあらゆるえりすぐりの食材を取りそろえ、食べる、買う、学ぶを一体的に提供できる施設づくりも検討していきたいと考えております。
また現在の市場は、県が設置して運営しております直営方式、レンタル方式でございますが、今後は官民の役割分担を見直し、市場の運営方法に民間企業の経営ノウハウを取り入れることはもちろん、施設整備に関してもPFI事業等の民間活力の導入も検討してまいりたいと考えております。
県中央卸売市場の再整備に当たりましては、生鮮食料品を扱う市場としての安全・安心の確保などBtoBの基本機能の強化は当然必要でございますが、加えまして、にぎわいの拠点となるBtoCに関して、現有施設の利活用の可否も含め、全体の土地利用、施設規模、事業手法等について具体的な検討を行ってきております。年度末を目途に構想案として取りまとめたいと思います。
滞在型観光の推進についてのご質問がございました。宿泊施設の整備の方向についてのご質問でございます。滞在型観光への転換は、本県観光における最大の課題でございます。そのため、客室数をふやすとともに外国人、家族連れ、若者、女性、ビジネス客など幅広いニーズにも対応できるよう、バラエティー豊かな宿泊施設を充実させることが有効と考えております。奈良県は量も少ないですが、この質のバラエティーも少ないと言われております。
本県では、これまでJWマリオットホテルの誘致や吉城園周辺地区と高畑町裁判所跡地へのホテル誘致を実現してまいりました。今後さらに県内主要観光地に幅広くホテルの立地を広げていくことが大事と考えております。
そこで県内市町村とも連携しながら、宿泊施設の候補地の情報収集を行った上で、これまでのホテル誘致活動で構築した関係事業者とのネットワークを生かして、海外の事業者を含め県内進出を検討するホテル事業者などにセールスを積極的に進めてきているところでございます。
一方、外国人観光客や若い女性などに人気のゲストハウスなどの小規模宿泊施設の開業もこの三年間で約七十件と増加をしております。県としても開業資金への無利子の融資制度を設けるなど、積極的に支援をしております。さらに、町家を活用した上質な宿泊施設をふやしていくため、空き家情報の収集・提供も進めております。
また本年六月に公布されました住宅宿泊事業法に基づく民泊サービスにつきましては、宿泊施設の選択肢をふやすことになり、魅力的な観光地でありながら宿泊施設が少ない地域などへも広がることで、本県の滞在型観光を促進する一助になり得ると考えておりますが、一方、宿泊客の安全・安心や快適性の確保、周辺住民とのトラブル防止も必要になってまいります。地域での調和を図りながら、良質な民泊サービスが提供されるように取り組んでまいります。県や保健所、所在地の市などに対する事務権限の移譲が法律で図られようとしております。
このように多様な宿泊施設の立地を促すことに加えまして、観光地といたしましてはWi‐Fi環境、決済システム、洋式トイレ、案内表示など、アメニティーを中心とした受入環境の整備も本県の滞在のために欠かせない取り組みでございます。この点も遅れてきておるように感じております。このように奈良県に欠けていたさまざまな面を補う取り組みを個別、具体的に積極的に進める必要があろうかと思います。奈良県観光のアメニティーのグレードアップを図り、観光地としての評判を高め、宿泊客の増加につなげるように図っていきたいと思います。
無電柱化の取り組みについてのご質問がございました。
道路の無電柱化は、良好な景観形成と観光振興という目的、また安全で快適な通行空間の確保という目的、また道路の防災性の向上という目的の三つの観点から、大変重要な施策でございます。特に歴史的文化資産に恵まれました本県にとりましては、良好な景観を確保し、国内外から訪れていただく多くのお客様をおもてなしする観点から、より一層重要な取り組みであると思います。
本県では、昭和六十一年度に大宮通りにおいて、初めて無電柱化に着手いたしました。その後、世界遺産の周辺地などで進めてまいりました。しかし、コストの面から電線管理者との調整に時間を要するなどの課題もあり、県管理道路での進捗状態は昨年度末で十五路線、約二十キロメートルという大変貧しい状況でございます。
今年度、十カ所で事業を行っておりますが、そのうち観光振興につながる良好な景観形成の観点では、県道橿原神宮東口停車場飛鳥線の明日香村飛鳥地内や県道三輪山線の桜井市三輪地内の二カ所で事業を進めているところでございます。
特に県道三輪山線は、日本最古の神社であります大神神社の参道になっているところでございます。今年度、全区間約七百メートルで事業化し、まちづくり連携協定に基づき、沿道住民との協働による景観形成に資する無電柱化を進めております。
無電柱化の推進に当たりましては、無電柱化の推進に関する法律により、都道府県も計画策定に努めるよう求められております。また本県では、多様な参加主体の連携・協働のもと、奈良ならではの美しい景観や環境の構築を目指す、きれいに暮らす奈良県スタイルを推進しております。こうした取り組みを踏まえまして、奈良県らしい無電柱化の推進方策を検討し、県の計画策定につなげてまいりたいと考えております。
次のご質問は、がん対策についてでございます。第三期奈良県がん対策推進計画の策定の方向性、目標についてのご質問でございます。
本県のがん対策は、第二期奈良県がん対策推進計画におきまして、がんにならない、がんになっても安心できる奈良県を基本理念に、医療、健康づくり、教育、雇用などの各分野の専門家や関係者が一体となって積極的に取り組んでまいりました結果、国が掲げましたがんによる死亡率二〇%減少目標を達成し、十年間の減少幅では全国一となりました。
第三期計画の策定に当たりましては、計画の推進体制であります奈良県がん対策推進協議会やその部会で議論を重ねているところでございます。八月に開催されました協議会の議論を受け、計画の方向性といたしまして、がんで亡くならない県日本一を目指し、がん医療、がん患者等への支援、がん予防・がんの早期発見などの分野別の施策に取り組みたいと考えております。
がん医療につきましては、がん診療連携拠点病院などにおける診療内容を把握・分析することで、医療の質の維持・向上を図り、その情報を県民にわかりやすく提供していきたいと考えております。
がん患者等への支援といたしましては、小児や若い世代、また働きながら治療を受けられる方など、多様化する患者さんのニーズに対応できるよう相談体制の整備を進めたいと思っております。
がん予防・がんの早期発見の取り組みにつきましては、その中でもがん検診の受診率向上に向け、受診される方の立場に立って、受診したくなるメッセージを届けたり、休日検診など受診しやすい環境を整えることが大切だと思ってきております。こうした取り組みが実現できるよう、市町村への支援や働きかけを積極的に行ってまいりたいと考えております。
次のご質問は、大和川流域における総合治水の推進に関する条例についてでございます。まずハード対策として、どのような、ためる施設の整備をしようとしているのかというご質問でございます。
平地でございますので、大きなダムなどはできません。昭和五十七年八月の大和川大水害を契機に、国、県、関係市町村で大和川流域整備計画を策定いたしましたが、その中で位置づけられましたためる対策のうち議員のご質問にある、ため池治水利用施設でございますが、市町村の対策実施率は平成二十八年度末時点で約四三%と低迷している状況でございます。低迷してきた主な原因といたしましては、ため池の管理者との調整の難航がございますが、上下流の市町村の間で、浸水被害に対する認識に差があることも大きな原因の一つだと思います。上のほうの市町村ではあまり浸水が発生しないので、浸水対策に不熱心なような傾向が見られます。
そこで、ためる対策の目標貯留量を確保するため、耕作面積の減少に伴い不用となった利水容量を治水容量に転換するなどの工夫により、ため池治水利用の促進を図りたいと思います。渇水ため池から洪水ため池に転換するという方法でございます。また新たな流域対策のメニューとして、水田貯留を条例に位置づけ、取り組んでいくことといたしました。洪水になりそうなときは水田に水を流して、少しでもためる対策をしようということでございます。
また今回の条例で、流域の上下流市町村と県が支川流域ごとに総合治水の推進に関する協定を締結し、計画を策定した上で、県は計画に基づく市町村の施策を積極的に支援することで、上下流市町村の認識の差を解消し、ためる対策の推進につなげていきたいと考えております。
総合治水の中で、ソフト対策はどのように取り組もうとしているのかというご質問でございます。どれだけ知恵を出して、難を逃れることができるのかといった課題であろうかと思います。
大規模な浸水発生時に県民の避難行動を促す減災に向けたソフト対策ということになりますが、ことし六月の水防法の一部改正を受け、本年度末までに県管理河川でも沿川市町村と洪水時の状況をあらかじめ想定し、情報を共有した上で防災行動の実施主体を時系列で整理する水害対応タイムラインと言われるものや、想定される最大規模の降雨に対するハザードマップの作成などの取り組み方針を大和川流域で取りまとめていこうと思っております。情報の共有とその意味を共通で認識するという基本的な作業をしていこうということでございます。
今後は、大和川流域全体の減災に向けまして、平成二十八年に国が設置しました大和川上流部大規模氾濫に関する減災対策協議会というものがございますが、新たに県管理区間の市町村を加えた協議会に拡大し、国管理区間と県管理区間が一体となった取り組みを進めたいと考えております。
このようなソフト対策とハード対策を効果的に組み合わせることで、昨今頻発する大規模な浸水被害が奈良県内で発生した場合においても、人的被害ゼロを目指しまして、安全・安心な県土づくりを実現したいと考えております。
次のご質問は、近鉄郡山駅周辺地区のまちづくりについてでございます。
近鉄郡山駅周辺地区のまちづくりにつきましては議員お述べのとおり、昨年八月に大和郡山市とともにまちづくり基本構想を策定し、次の段階である基本計画の検討を行っております。加えまして、本年四月に県と大和郡山市と近畿日本鉄道株式会社の三者が連携協定を締結し、今あります駅を北のほうへ移設することを中心としたまちづくりを具体的に検討するための体制を整えたものでございます。
また本年三月から八月にかけまして、大和郡山市が開催されましたワークショップでは大変貴重なご意見が出ております。毎回、市民の皆様が活発に議論を重ねられており、その報告をその都度受けております。例えば、望ましい駅前広場の使い方、駐車場や送迎スペース、観光案内所等周辺に必要な機能の確保、矢田町通りも含む駅周辺道路のあり方などでございますが、残念ながら、近鉄郡山駅周辺には全くこういう機能がございません。なんとかそのような、市民が憩える場所をつくりたいというワークショップ参加の市民の方の思いは切実に感じるところでございます。これらを参考に今後速やかに基本計画を取りまとめたいと考えておりますが、駅移設に伴う周辺の道路や駅前広場の構造をどうするかといったハード的な課題が横たわっております。現在の三の丸バスターミナルや駐輪場、立体駐車場が立地している一帯を新しい駅前広場として再整備するに当たりましては、限られたスペースを有効に活用することが必要でございます。
そこで、アイデアだけでございますが、例えば地下に駐車場や送迎スペースを配置できないか、地下駅前広場という構想でございます。駅の西側からも踏切を渡らずにこの地下部分へアクセスできないかといったことも検討しています。加えて、地下にも改札があれば、地下駐車場から駅へ安全に移動できるのではないかといったアイデアも出ております。また地上では、郡山城へのアプローチも必要であろうと考えております。
矢田町通りにつきましては、拡幅しないことを前提にしておりますが、駅東側の商店街はできるだけ自動車の通行を抑制し、歩いて楽しいにぎわいのあるまちづくりを検討しており、駅西側では歩行者、自転車、自動車が錯綜し、危険な状態であるため、住民の利便性を確保しつつ、一方通行化による危険の解消ができないかなど、周辺の道路の通行方法の見直しも含めて検討しております。
こうした検討におけるアイデアの段階でございますが、その具体化についてはまだまだ難しい課題が次から次へと出てくる状況でございますが、私を含めました担当部局において真剣に具体化に向けた検討を進めております。近鉄郡山駅周辺が歩行者中心の城下町にふさわしいにぎわいにあふれた、たたずみやすいまちへとリニューアルすることを目指して、大和郡山市や近畿日本鉄道株式会社と連携・協力しながら、年度内には基本計画が策定できるよう全力で取り組んでまいりたいと考えております。
最後のご質問は、教育長がお答え申し上げます。
○議長(岩田国夫) 吉田教育長。
◎教育長(吉田育弘) (登壇)三十九番小泉議員のご質問にお答えをいたします。
私には小学校教員の英語の指導力向上のために、県教育委員会として、どのように取り組んでいくのかとのお尋ねでございます。
社会の急速なグローバル化の中で、国際共通語としての英語によるコミュニケーションの必要性はますます高まり、実用的な英語力を身につけることは子どもの将来の可能性を大きく広げるものと認識をしております。
議員お述べのように、平成三十二年度から全面実施される新学習指導要領では小学校三、四年から英語の活動が、五、六年からは教科としての英語が新たに追加され、英語学習の充実のためには小学校教員の指導力の向上を図ることがこれまで以上に求められています。
そこで県教育委員会では、平成二十六年度から英語学習の早期化及び内容の高度化に対応するため、奈良市、明日香村、御所市の三地域を指定し、子どもたちが生き生きと英語に慣れ親しむ授業づくりや、音声・動画を活用してわかりやすく英語が学べる教材などの研究開発に取り組み、研究発表会等を通して、県内の小学校教員にその成果等を普及をいたしております。
また、奈良教育大学と連携して、英語指導パワーアップ講座を実施し、各郡市の英語教育の中核となる推進リーダーをこれまでに延べ百二十二名育成するとともに、その推進リーダーの模範授業による授業研修を各地域で実施をいたしております。
教科としての小学校英語は、学級担任が中心となって授業を担当するため、英語での会話の指導に多くの教員が不安を感じていますが、来年度から教員免許状更新講習として、小学校英語教育の講座を教育研究所で実施することを計画しており、平成三十年度、平成三十一年度の二年間で、約六百名の小学校教員に対して英語の指導方法のスキルを身につけていただく予定でございます。
今後、英語学習におきましては小学校から中学校への円滑な接続を図ることも課題であると認識をいたしております。そのため、平成二十七年度から中学校、高等学校の英語の教員免許を有するなど英語に高い専門性を有する小学校教員をこれまでに十三名採用をいたしております。教育内容や指導方法について、小中が共通理解を持つために中学校との連携を強化する役割を担う人材として、現在育成しているところでございます。
以上でございます。どうもありがとうございました。
○議長(岩田国夫) 三十九番小泉米造議員。
◆三十九番(小泉米造) 私の質問時間があと一分足らずでございますので、私も予算審査特別委員会に入っておりますので、再度質問したいと思っております。それでは知事、教育長、本当にご答弁ありがとうございました。よろしくお願いいたします。終わります。